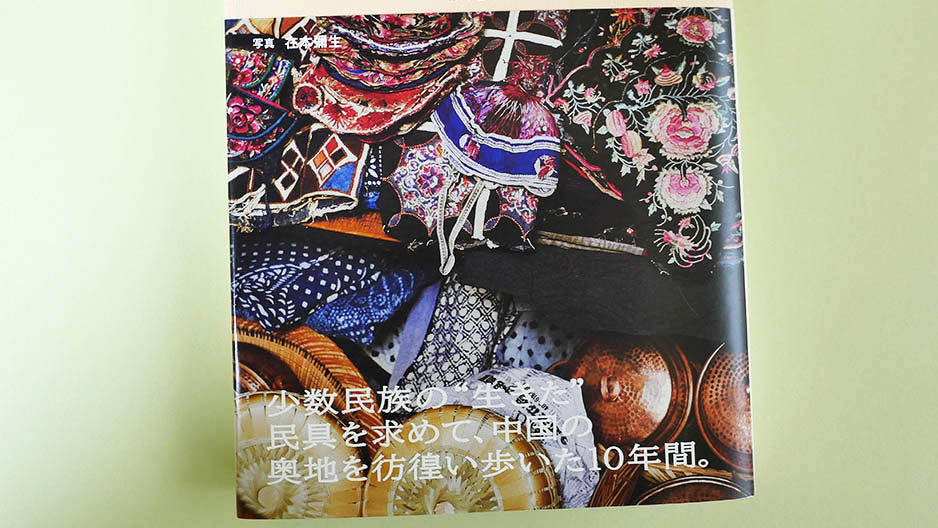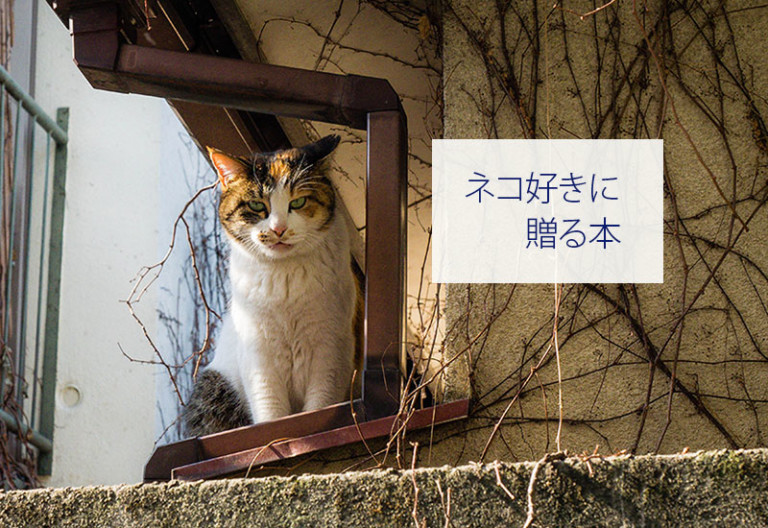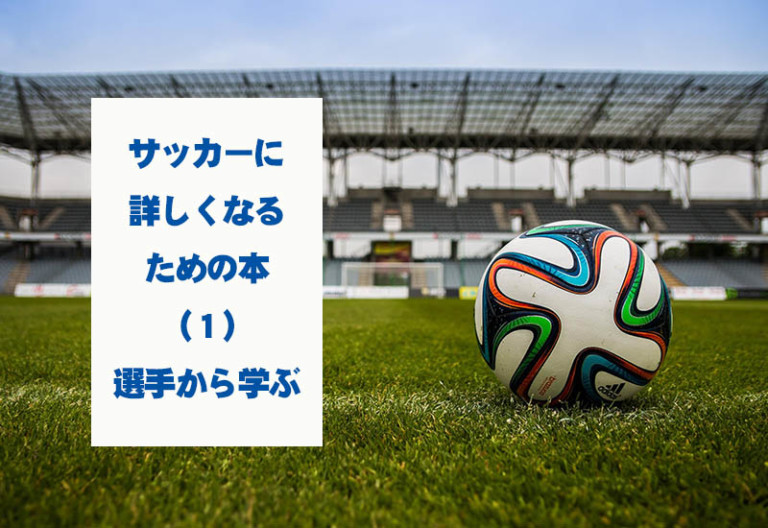旅はまだ健在なのか
わたしはまったくもって食通だとか、グルメではありません。
“どこそこのなにがおいしい”とか、“お寿司ならここじゃないとダメ!”とか、そういったたぐいのこだわりもない。
ただ単純に、おいしいものが好き、おいしければいい、そんな具合のふつうにいる食いしん坊なのであります。
しかしうちの嫁さんにいわせると、なかなか手強いそうなのだ。
なぜか・・・?
それは、嫁さんが出してくれた食事を食べるとき、ふいに、「あれ?今日の枝豆いつもと違うね!」とか、「ときどきお弁当に入っている、あれ、おいしいよね」などと無意識に口走ったりするのだけれど、それが的を得ている、つまり、それが実際にいつもと違うものであったり、ちょっと奮発して買った食材だったりするそうで、それが怖いというのです。私は何もそんないいものを食べたいといっているわけではないけれど、そういった一言で返されると、下手なものは出せないなと思って、それがために怖いと思うのだそうです。
インスタントコーヒーの宣伝ではないが、嫁さんにとって、私はいわゆる“違いの分かる男”ということなのだろう。
しかし別に子供の頃からも、大人になってからも、そんなに意識して味覚の違いをかぎ分けようなんて思ったことはない。嫁さんは、私の実家が和菓子屋をしているので、そういった遺伝子があるのではないかとか、そうはいってもおいしいものを食べてきたんだろうなんて邪推したりしている。でも、小さい頃は和菓子のあのやさしい甘さは理解できなかったし、友達と同じように駄菓子を食べて育ってきたのだから、そこまで敏感なはずではないと思う。
でも、それでもどこか違いがあるのだとすれば、それは母親が手作りしてくれた食事をほぼ毎日食べていたからであろうか。
実家は和菓子屋で自営業。
ちっとも働かないオヤジに手を焼きながら、母は苦労して仕事と主婦業など、すべてを一手に引き受けていた。家業の和菓子屋がつぶれかけたときなどもあったし、人に騙されたり、裏切られたことも一回、二回なんて生易しいものではない。人が良いというのか、お人好しというものなのか、それがために背負ってしまった苦労も多かったと思う。
しかし、そんな苦労ばかりの中にあっても、家族の食事はしっかりと作ってくれたこと、今思うとこれはすごいことだと振り返る。
自営業で、住み込みの職人さんもいたから、家族の分も含めて大量にワーッと作るわけで、決して繊細とはいえないけれど、でもやはり、今思うと、よくそこまで作ってくれたと思うし、よくそんな時間があったものだと感心をするのであり、そして感謝しかない。
恐らく、そういった母の心持によって作られた、いわゆる“おふくろの味”というものが、きっと私の味覚を育ててくれたのだろうと思う。
嫁さんにはちょっと厄介な舌ではあるかもしれないが、それは母の愛情と創意工夫の賜物であるのかもしれない。
たべもの

Netflixで、中国の郷土料理を取り扱ったドキュメンタリー番組がある。
邦題は『美味の起源』
これがまためちゃくちゃ面白い。
そして、その景色がとてもいい。
それぞれの料理も、とても手が込んでいて、とにかく下ごしらえがすごいのだ。
下ごしらえのような地道な作業は、日本人のお家芸かと思っていたけど、なんのなんの、このドキュメンタリー番組を見る限りでは、はるかに中国のほうが上だ。徹底してこだわっている。ルーティン、使う器具、季節や時間帯など、全てがその料理、食材のために貫かれている。これは正直恐れ入る。
ということで、著書を
このブログは“エア本屋”。
やはり本のご紹介をせねばなりません。
映画を観終わった後、やはり何か一冊でも読んでみようと、『へたも絵のうち』を手にすることにしました。
こちらの『へたも絵のうち』は、日本経済新聞の名コーナーである「私の履歴書」に本人が話したものをまとめたもの。おそらく口述筆記なのだろうけども、そこは本人の意図や雰囲気を崩さないように、もちろん誇張もなく真実が語られている。
生い立ちから東京藝術大学へ進学していく過程や、そこで出会った青木繁などの学生との交流やエピソード。このあたりの交流の話は、日本の近代美術史の貴重な裏話ではないかと思います。
熊谷守一氏は、年の離れた女性と結婚後、何人か子供をもうけているものの、そのうちの数人を亡くしています。そのときの悲嘆にくれたお話などは、読んでいてもその悲しみが伝わってくる。ありていに言えば、芸術家であるための人生の流れの一つなのかもしれない。が、しかし、それは熊谷守一という人物の一生を振り返ってみるからこそ感じるものであって、それはそれ以上の人生の試練であって、深い悲しみなのだ。
そういったいろいろなことを経ながら、年齢とともに画風が変わり、そして、年老いてからますます名声が高まっていくというその孤高の存在は、なかなか他に類はない。
戦後を代表する芸術家が、どのような道を歩み、どのような制作活動をして来たのか。
晩年はどのように日々を送っていたのか、映画も併せて読んで、観てほしいなと思うのであります。
https://www.netflix.com/jp/title/80991060
その他の関連本・音楽
この記事の読書人

瀬戸郁保
東洋医学・中医学を専門にしながら、興味のある分野のものをまたいで読んでいる雑食系です。人生後半戦に入ったので、ブログもどこまで続けるのか考えるけれど、それはそれで昔書いたブログの記事を読むと、やっぱりよかったなって思う日々。